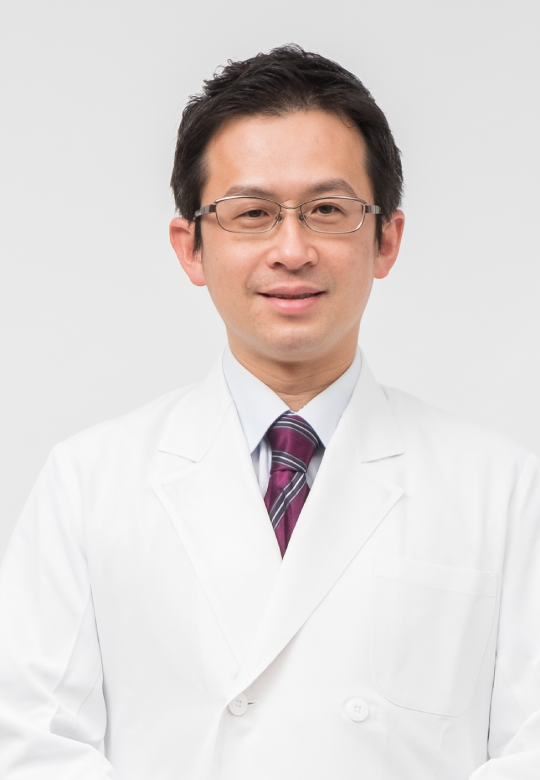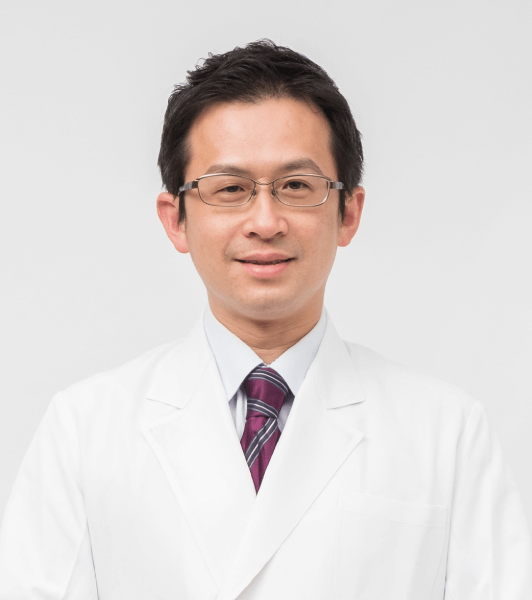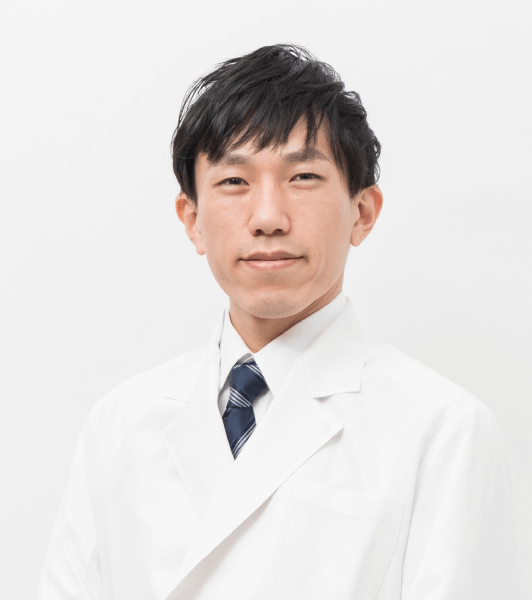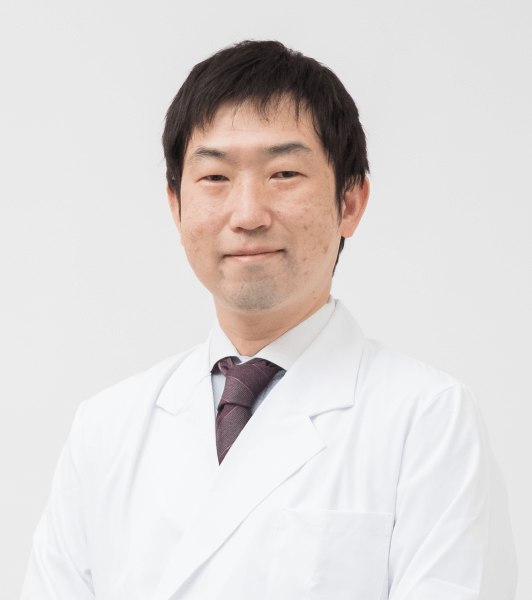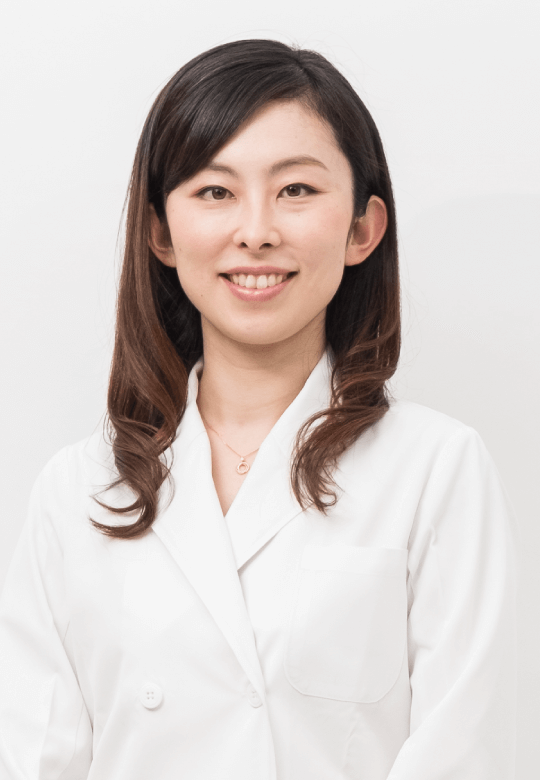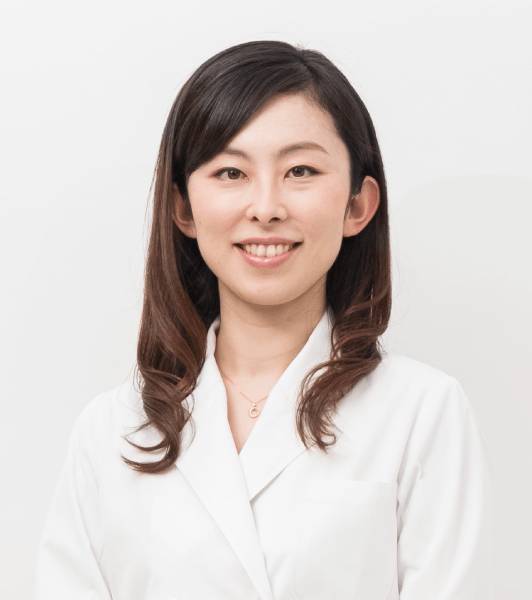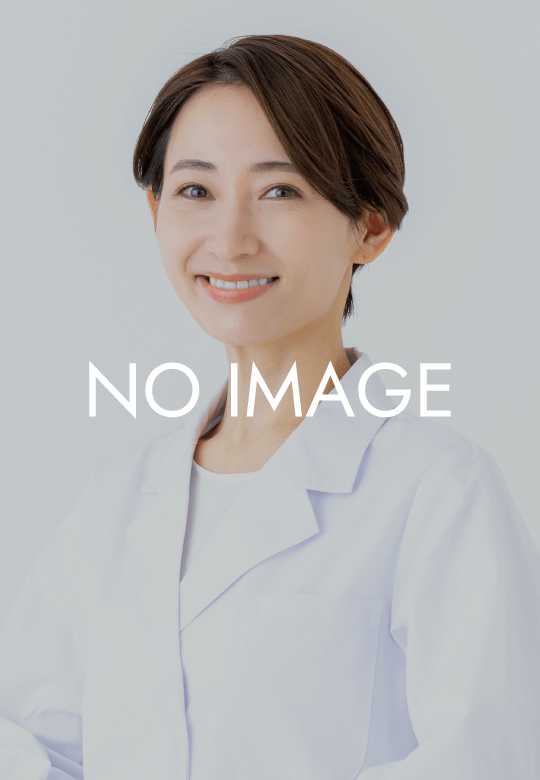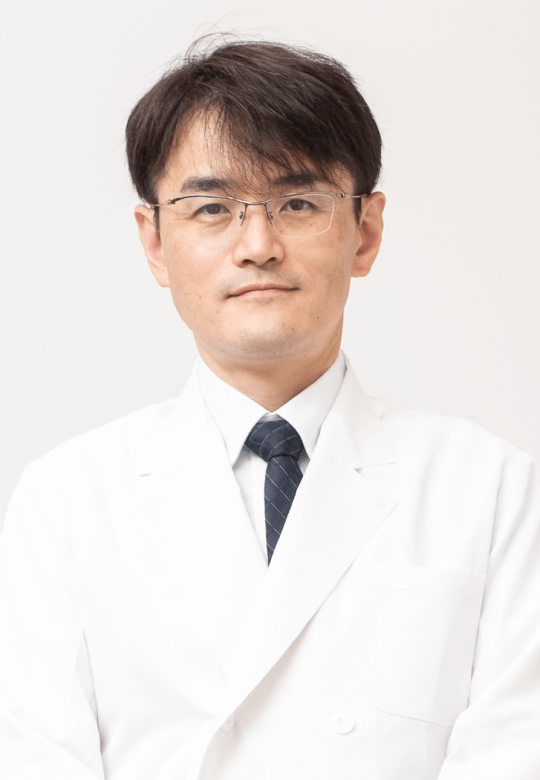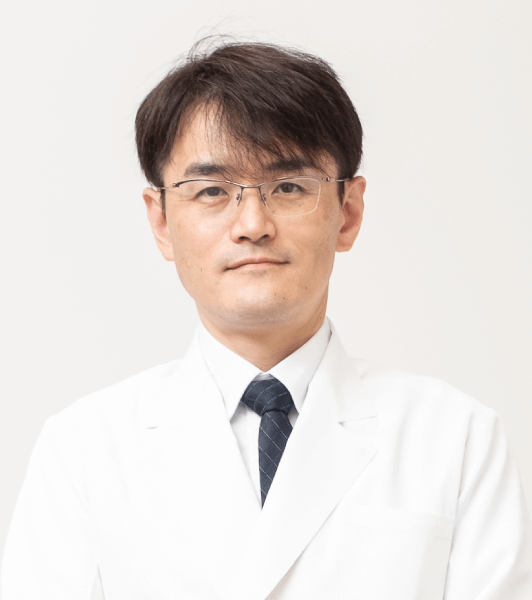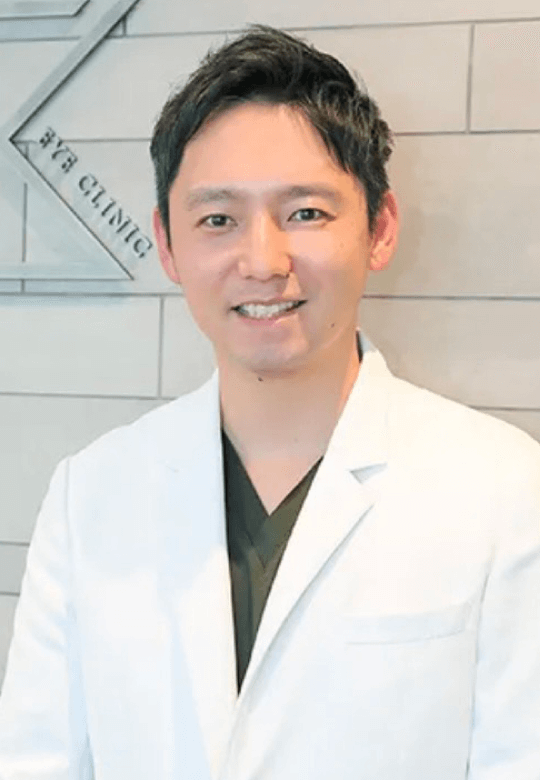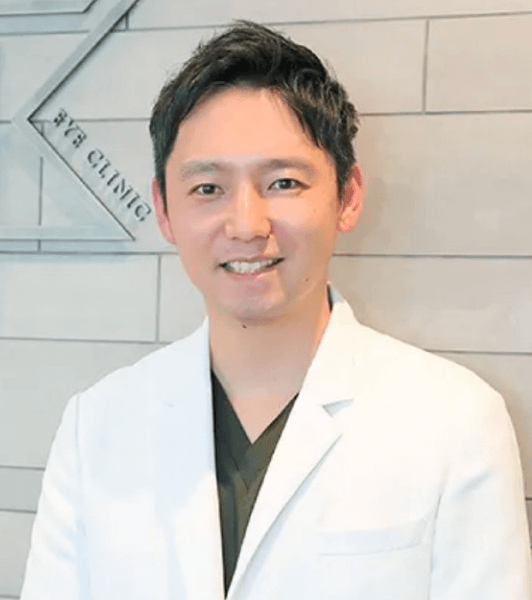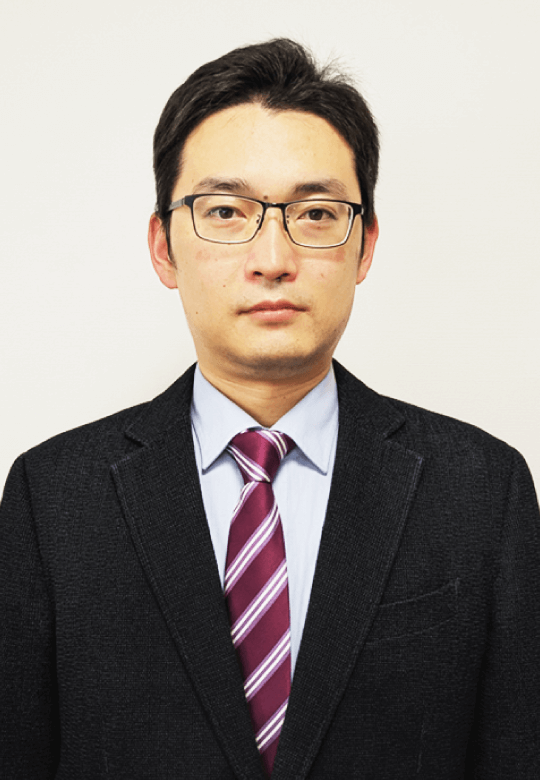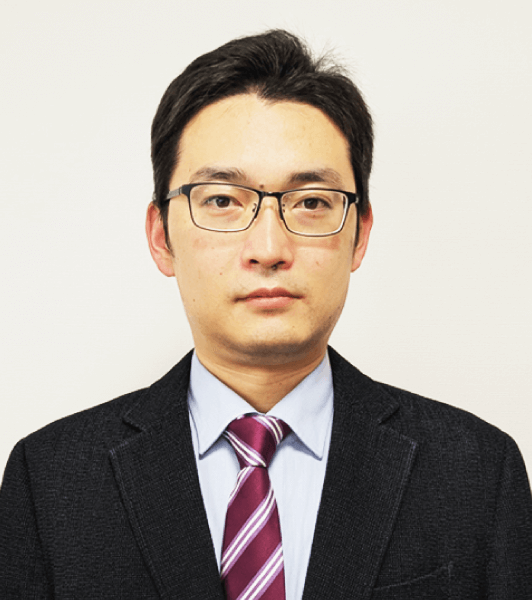インタビューInterview
若手医師のキャリア構築を
支援する研究環境。
工学博士

現在の所属を教えてください。
中京眼科 視覚研究所です。
これまでの経歴を教えてください。
共同研究先である信州大学工学部で在学当時から中京グループとの共同研究を行っていました。学位取得後、視能訓練士の資格を取得し、中京眼科視覚研究所の研究員として研究のサポートなどを行っています。
工学部という学問について簡単に教えてください。
科学と数学を使って、社会に役立つ技術やシステムを設計・開発する分野です。
機械、電気、化学、建築、情報システムなど多岐にわたる専門分野があり、生活の問題を解決するための知識とスキルを学びます。例えば、橋やビルの設計、スマートフォンの開発、環境に配慮したエネルギーシステムの構築など、私たちの生活に密接に関連しています。


信州大学工学部との共同研究のきっかけを教えてください。
20年程前に信大工学部の教授が色覚異常の方が見ている感覚をシミュレーションしたいと、中京グループ創設者であり、色覚専攻の市川一夫医師と連携を図ったことがきっかけです。
これまでどのような研究を行ってきましたか?
白内障の進行度を定量的に評価する画像処理アルゴリズムや、色視力・色視野など検査に関する機器の研究と開発、色覚の加齢変化を補正した術者の視機能サポート、色覚機能を補助するスマートフォンアプリの開発などを行ってきました。
現在は白内障の画像診断機器とスマートフォンアプリの開発に注力しています。
共同研究のやりがいや魅力を教えてください。
学問の壁を越えた研究ができることが一番の魅力だと思います。眼科医学の視点から、『もしこのような検査やデバイスがあれば…』といった問題は、1つの学問では解決が難しいかもしれません。しかし、共同研究で異なる分野の専門家と協力することで、実現の可能性が大きくなります。
また、お互いの学問を横断的に研究が進んでいくので、双方の知見が広がり、知らない世界を知ることができます。そのような中で新しいアイデアが生まれ、そのアイデアを具現化できることは非常に面白く、やりがいを感じています。
中京グループで研究を行うメリットについて教えてください。
中京グループの強みは、提携施設のネットワークと各分野のスペシャリストの豊富さにあります。これにより、技術検証を迅速に行い、多くのデータを基にした研究にスムーズに繋げられる点が大きな魅力です。
最近では、グループ所属の佐藤裕之先生を筆頭に、前視野緑内障の早期発見の為に色視野を検査する機器を開発し、いくつかの医療機関でデータを取得し、有効なデータを示しました。
研究テーマが数多くあるので、若手の先生方のキャリア構築にも適した環境だと思います。
中京グループへの所属を考えている
医師の方々へメッセージをお願いします。
中京グループでは、臨床だけでなく、興味のある研究に挑戦できる環境が整っています。
信州大学との共同研究のように、「あったら良いな」というアイデアが実現する可能性も多くあります。眼科医学の発展に向けて様々な角度から挑戦してみたい方は、ぜひ私たちと一緒に未来を切り開いていきましょう!